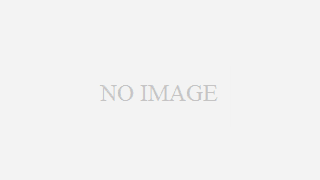 -
- 第38回東京国際映画祭で『パレスチナ36』が東京グランプリ受賞
2025年10月27日から11月5日まで、第38回東京国際映画祭が開催されました。15作品が正式出品された今年のコンペティション部門には、108(110)の国と地域から1970本(2023本)の応募がありました。*()内は昨年数※邦画作品の...
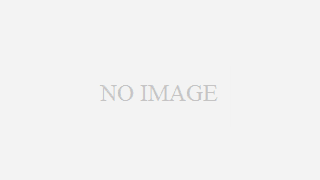 -
- 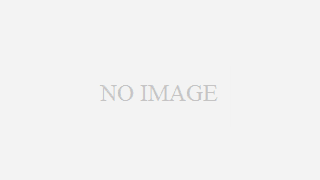 -
-  -
- 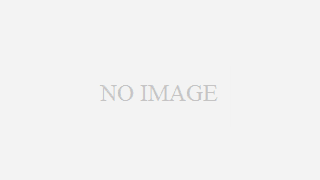 -
- 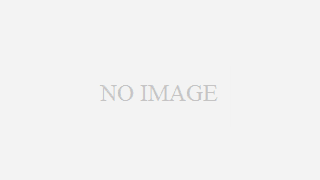 -
- 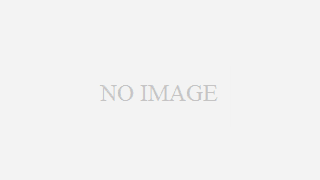 -
- 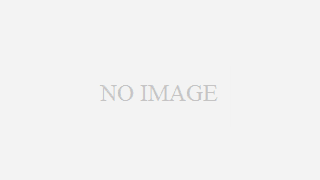 -
- 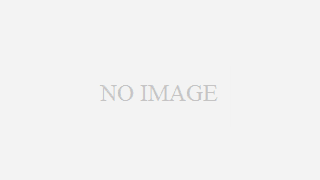 -
- 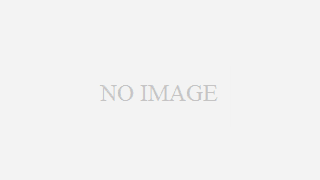 -
- 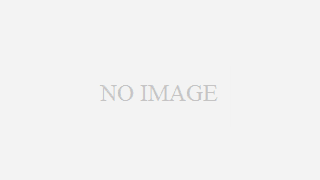 -
- 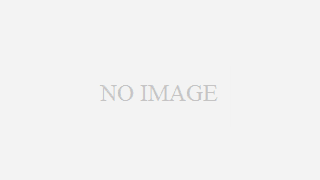 -
- 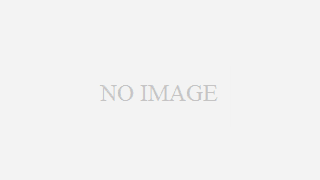 -
- 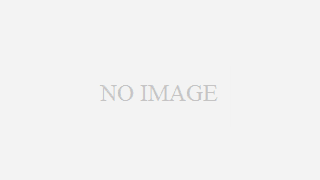 -
- 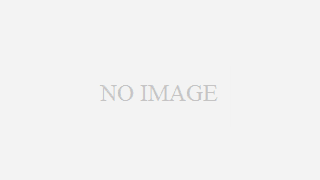 -
- 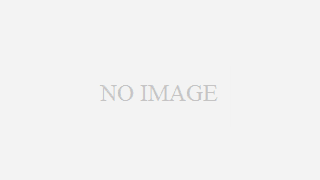 -
-